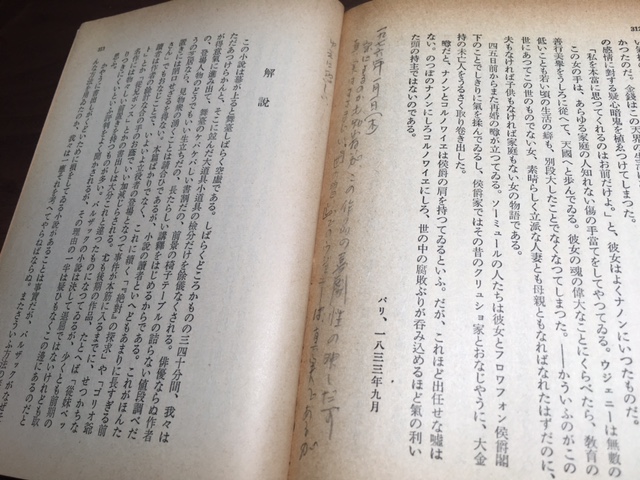佐伯一麦の短篇「朝の一日」を読みました。
これは「海燕」1986年12月号が初出で、単行本『雛の棲家』(福武書店、1987年)に収められ、今は『日和山』(講談社文芸文庫、2014年)で読むことができます。
内容は、主人公の鮮(あきら)が仙台の町で朝早くに新聞配達をする。たったそれだけですが、その過程で胸にさまざまな思いが去来する、というもの。鮮の知り合いの女子が妊娠したことが周囲の少年たちの間で話題になっていて、妊娠させたのは鮮であるという噂が立っています。しかしそれは間違いで、鮮は女子(光枝)に思いを寄せながら、チャンスはあったものの抱く勇気はありませんでした。そして最後は、新聞配達を終えた後、一人で私生児を生むことになる光枝のことを思い、「光枝に逢いに行こうか」と考えるところで終わります。「仙台」と具体的に地名が書かれているわけではありませんが、佐伯が私小説の書き手であることを考えると、その舞台が仙台であるのは間違いありません。
この小説について、阿部公彦は『日和山』の解説で「処女作」と述べていますが、その根拠は示されていません。佐伯が公に発表した最初の小説は「静かな熱」という短篇で、これは1983年に第27回かわさき文学賞コンクールに入選しました。「静かな熱」は高校時代に書いたもので、厳密にはこちらこそ「処女作」と呼べそうですが、その内容は「朝の一日」に酷似しています。
朝の新聞配達の模様を描いている点、知り合いの女子(「静かな熱」では「光江」)が妊娠し、自分が子の父親だと噂されている点、最後に女子に逢いにいこうと思って終わる点も同じです。また、新聞の配達区域が刑務所(仙台市の宮城刑務所)の近くであることや、そのコンクリート塀に「S裁判粉砕!I被告強制移送絶対阻止!!」とあること(「静かな熱」では「S裁判粉砕!I被告強制送還阻止!」)、配達先の家の窓に「カネカエセ」と書かれた貼り紙があることなど、細部もほぼ同じです。
「朝の一日」は、言わば「静かな熱」を改作したものです(その旨は『日和山』巻末の佐伯年譜にも記されています)。佐伯はその後、これにさらに大幅に手を加えて『ア・ルース・ボーイ』に結実させます。『ア・ルース・ボーイ』にまで言及すると長くなってしまいますのでこの辺で止めますが、『ア・ルース・ボーイ』には「狭山裁判粉砕! 石川被告強制移送絶対阻止!」と書いてあり、「S裁判」は狭山事件の裁判だったことが分かります。