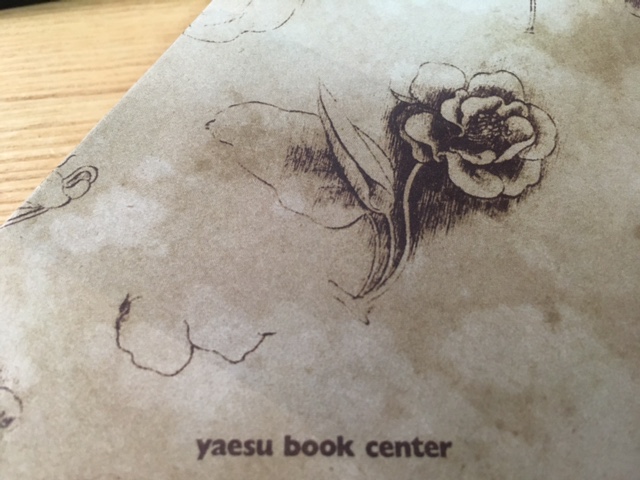榎本博明『内向性だからうまくいく』(日本実業出版社、2002年)は、内向的な性格の人が自分を受け入れ、長所をうまく活かして生きていくための助言をする本。章ごとでテーマが分けられ、助言を述べる節が一つにつき2ページでまとめられており、読みやすい。中に「外交型をうらやむことはない」という章があり、それ以外でも全体に外向型人間を批判的に書いているところがあるが、恐らく内向人間の私にはためになることがけっこうある。
「つい他人と対決的な姿勢をとってしまう」というタイトルの節があるが、これを目次で見て気になった。私自身、そういうつもりはないのに、会話の過程で気がついたら相手と対決する位置に立ってしまっていたことが、これまで数え切れないくらいあったのだ。
気がつくと敵対してしまう過程を、著者はこう書いている。
適応に時間がかかる内向的人間には、周囲の状況が十分呑みこめない限りそれに合わせられないという特徴がある。納得しない限り積極的に同調できないという生き方は、けっして否定すべきものではない。軽率に周囲に合わせる風潮のある今日、むしろ気骨を感じさせ、頼もしいくらいだ。
だが、忍耐力に欠ける者は、自分の適応の遅さにいらつき、ライバルの軽薄なまでの適応の速さにあせりを感じる。それがともすると周囲に対する否定という短絡的な心理を生むことになる。
つまり、自分に対するいらだちを、無意識のうちに、適応を強いる周囲の環境に対する攻撃心へと転化してしまうのだ。そして、意に反して、周囲と対決的な姿勢をとっている自分を発見して驚くということになる。
周囲に腹が立つというより、周囲を十分に呑み込めない状況への苛立ちが、周囲への対決の姿勢になってしまうわけだ。
過去を振り返ると、そういう姿勢をとってしまったばかりに場の雰囲気が悪くなったり、その場にいた人からの信頼を失ったりと、ろくなことがなかった気がする。とはいえ、適応が早い人たちが悪いわけではない。一人勝手に失敗し、苦しむのが内向人間だと思う。